【勝手気ままに映画日記+山ある記】2025年6月
 |
| ヨセミテ公園からのシェラネバダ山脈? |
6月は2日から9日までアメリカ・シェラネバダ山脈のヨセミテ・キングスキャニオン・セコイアの3国立公園内の5コースハイキングから始まりました。晴天(この時期カリフォルニアには雨が降ることはないのだとか)、山脈の雪解け水がごうごうと流れる滝の数々、咲き乱れる花々や、セコイアの樹齢何百年~2千年の圧巻に目も耳も全身を奪われるような至福の時を感じながら…。詳細については以下のサイトへよろしく
ヨセミテ・キングスキャニオン・セコイア国立公園:滝と花めぐりハイキング5日間:2025/6・2~9
【6月の山ある記】
6月18日 焼岳北峰(2444m)
前日より松本駅近くエースイン松本(部屋は小さいがすこぶる居住性の高いさすが日本のビジネスホテル)に投宿、当日は朝5時のチェックアウト・専用バス(1人2席、ゆったりして乗り心地は最高)での出発となる。
久しぶりのCTツアー。参加者は12名(女性8人・男性4人 平均年齢は案外高そう。常連っぽい方もちらほら)現地ガイドのKさん(痛風の痛みをロキソニンで押さえて?おまけに半月板もないんだとか)、添乗員もベテランSさん。
6:30上高地帝国ホテル前➡6:45焼岳登山口➡9:30焼岳小屋(休憩)➡(連続したハシゴを越えて)➡10:00イワカガミ・イワヒゲの群生地➡10:50焼岳直下➡11:30焼岳頂上(2444m)➡12:00下山開始➡12:46雪渓を越える➡(ちょっとこの間胃腸トラブル?あり)➡15:00新中の湯登山口へ下山(駐車場へ)
実は前々日まで、ヨセミテの疲れが抜けない?鼻風邪っぽくたまに咳も出るし、やや心配の状況。それでも前日は夕方の集合なので立川で映画を1本見てからガラガラのあずさで松本へ。でも夕飯は食べる気も飲む気にもなれず駅前のコンビニでサラダパスタやヨーグルトなどを買って夕飯後、ゆっくり入浴だけして9時頃には入眠剤も飲んでねてしまった。3時半ごろ快調に目を覚まし、バナナ・スープなどをちょっと飲み、薬ものんで5時出発。
テルモスに氷を詰め今日はコンビニで買ったゆず・レモンサイダーを入れてみる。これは気軽に飲めて甘すぎず大成功。今年の夏の定番になりそう(ヨセミテのパインジュースも美味しかったが、これは日本にはないみたい)
懐かしい!(ホントに久しぶりに来た)帝国ホテル前から、すがすがしい森林地帯を歩き梓川?上高地の景色を堪能しながら焼岳登山口へ。ここからもしばらくは森林地帯を緩やかに登っていく感じを楽しめる。天気は快晴、温度も高そうだが森林の中を歩いている限りは快調。途中ヘルメットを装着、間に細いハシゴの連続や、岩場にはった鎖などもあるが、まあなんのそのツアーだととっつきで休めるのでかえってラクな気もする。
森の中を歩いて森林浴/火山監視カメラ/ハシゴ場で上り待ち
途中からぐんと眺望がよくなる。正面は笠ヶ岳あたりにはけっこういろいろ花が咲いている。途中からはイワカガミがたくさん。焼岳の全貌が見えるあたりにはイワカガミとイワヒゲ(白い小さな釣り鐘型の花がいっぱい)の群生地帯を楽しんだりもして、下り登りのはて、いよいよ焼岳最後のザレ土の山塊にとりつく。
山頂からの景色西穂山荘から西穂~奥穂~釣り尾根~前穂あたり/槍もちょっと見える
山頂光景 平日だが登山者がけっこういた途中ほんのちょっとだが雪渓歩きも…
ふたコブの間に噴煙が上がっている。あそこを通り抜けてきたんだ、と見上げる。
CTツアーは割合客管理を丁寧にするので歩く順番(班)も決められている。前にどんな人が来るかによってもけっこう気分に差があり、皆さん前とあけないように引っ付いて歩いているので一人に慣れた私としては少々疲れ、いつも私の前が少しあいてしまうという感じなので、今回もこのあたりからはガイドの直後を志願。自らペースメーカーを務めることに。自分ではかなりゆっくりゆっくり歩いたつもりだが、結局ヤマップによれば90-110%の標準値で遅くはない。11時半焼岳北峰到着。なお、南峰(1m高い)は火山のために登ることはできない。
レモンサイダーの飲みすぎ?かあまり食欲はなく、昨夜買ったチュロキー(パン)と家から保冷剤付きで持参した葡萄などで昼食。
展望のすばらしさにたくさん写真を撮る。ピークファインダーでも撮ったのだけれどこれは残念ながら保存に失敗。12時には下山開始。12人のツアーは経験者も多いような口ぶりだったが、下山に際しては2本ストックを前かがみについて一歩一歩えっちらおっちらという感じの方もいて、その後ろに着いてしまったのでかなりのスローペースで、気を抜くと前の方のストックにぶつかりそうにもなるし、私としてはむしろバランスがとりにくい感じでけっこう疲れてしまう。そのうちに水の飲み過ぎか胃が例によって働かなくなり、途中で薬を飲んだのだがそれがかえって裏目に出た(キリマンジャロの時もそうだった)のか「山酔い」っぽくなってエズいてしまい、添乗員Sさんのお世話を受け心配されてしまう。ちょっと小休止、水を飲むと胃におさまったので元気回復、あとは普通に歩き、少し先で休んでいた皆さんに合流し、ここからはまたまたガイドの直後を選んで無事に下山。後半下り道では花の写真や噴煙を捲き上げる焼岳を撮ったくらいで写真もなく、なんか疲れきって下山した感じ。やはり夏はつらいかなあと、少々次回以後が心配にもなっているところ。
6月は結局この焼岳で、山は終わり…
6月の映画日記・・・完成版です!
①秋が来るとき ②盲目の目撃者(Bhramam)③ガールズ・ウイズ・ニードル ④おばあちゃんと僕の約束⑤国宝⑥テルマがゆく!93歳のやさしいリベンジ⑦舟に乗って逝く(乗船而去)⑧島から島へ(由島至島)⑨ラブ・イン・ザ・ビッグシティ➉アンジーのBARで逢いましょう⑪シアトリカル唐十郎と劇団唐組の記録⑫セルロイド・クローゼット⑬アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓⑭ルノワール⑮ラ・コシーナ厨房⑯フロントライン
中国語圏映画⑦⑧
日本映画⑤➉⑪⑭⑯
その他のアジア映画④⑨
ドキュメンタリー映画⑧⑪⑫
と、まあこんな感じの6月でした。①④⑥⑦⑩は高齢者や終活?(しかも皆女性!)をテーマにした映画で、そういう傾向の映画が増えているのか、それとも私の目がそっちに向いてしまっているのか…。真面目な?終活映画も参考にはなるのだけれど、やはり元気が出るのは⑥や➉のように年齢をモノともしない(人に頼ることも含めて)しっかり自立の人生を歩む女性の姿ではあるのだけれど、果たして自分が将来そうなれるのかどうかはね…(そういうことを気にするようになったということが「お年頃」の証左なんでしょう⤵😞
★はナルホド! ★★はイイね! ★★★はおススメ!(モチロンあくまでも個人的感想です)各映画の最後の番号は今年になって劇場で見た映画の通し番号。
各文中の赤字部分は、その作品などに言及したページへのリンクをはったところです。
⑯フロントライン
監督:関根光才 出演:小栗旬 松坂桃李 池松壮亮 窪塚俊介 森七菜 桜井ユキ 吹越満 光石研 滝藤賢一 2025日本 129分 ★
過ぎてしまえば「昔のこと」みたいになっている?コロナ禍の中でも2020年2月、記憶にもまだ新しい豪華クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号(乗客3711名)の100あまりの感染陽性者を乗せての横浜港入港と、対応したDMAT(災害対応の医療者ボランティア組織)、厚労省の役人、の10日余りの活動を凝縮して「事実に基づいて」構成したドラマであることは周知のとおり。私から見れば「若手」と思った小栗、松坂を中心に現場指揮をとるのが窪塚洋介、前線で医療活動にあたるのが池松というわけで、これを上から阻止するような頑迷な高齢の役人(こういう映画のかつては定番?)などというものは出てこないのだが、思えば久しぶりに映画画面で見た小栗も、窪塚もしっかり40歳は越え、30代の松坂や池松も含めしっかり「オジサン」というか中年に達しているのであったWWW。映画そのものはこういう映画の作り手である人々(「劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命」の増本淳プロデューサーが企画・脚本・プロデュースだそう)の手慣れた技?によって、最初は「自分たちの出動」に疑問をもつDMATの責任者と、法に縛られ越えよとしない役人との対立?で始まると見せ、次第に彼らが協力体制を築いていく理解の過程とか、面白がっていたふうの報道陣のひとりとDMATに医師の意思疎通とかをうまく描いて、実話ベースゆえか本当の敵役というのも登場しないし(敵役は無責任な言動をまき散らし沙医療従事者への差別をあおるSNSということになる)、浅い感じではあるけれど過不足なく事件を娯楽化しているのはまあ、なかなか…ではある。TOHOシネマズ6本見れば1本無料のポイント鑑賞で見た。土曜夕方からの回は(当然)満席に近い込み方。
(6月28日 府中TOHOシネマズ 171)
⑮ラ・コシーナ厨房
監督:アロンソルイスパラシオス 出演:ラウル・ブリオネス・カルモラ ルーニー・マーラ アンナ・ディアス モーテル・フォスター ローラ・ゴメス オデット・フェール エドヴァルド・オルモス 2024アメリカ・メキシコ 139分ほぼモノクロ ★
原作は英国の作家アーノルド・ウェスカーによる1959年初演の戯曲『調理場』だそうだが、現代のニューヨーク・タイムズスクェアのレストラン(決して格式のある店ではなくて観光客向けのむしろ大規模大衆レストランという感じ)の調理場を舞台にメキシコ人、アルバニア人、モロッコ人など移民の調理人・ウェイトレスが入り乱れ喧噪、喫煙、怒鳴り合いというなんかもう滅茶苦茶な感じの厨房風景。発端はメキシコからやってきたエステルが主人公ペドロを訪ねてこのレストランにやってきて人違いで厨房に雇われるところから、おりしも昨夜閉店後のレジから800ドル余りの売り上げが消え、店主の命令でマネ―ジャーは従業員一人一人に面接をして犯人探しをすることになる。チェリー・ウォーター?のマシーンの故障とか、調理人どうしのいがみ合い、その中で店を出て恋人との暮らしを夢見るペドロと、妊娠してしまった恋人ジュリアはーペドロに身や心を寄せているようでありながらも、彼の夢に乗ることはなくそこには何か秘密もありそうなというふうに描かれる(演じているのはルーニー・マーラであまり彼女がよく演じるような役柄ではないと思うが、もちろんさすがにうまい)。調理人たちは字幕ではメキシコ人、モロッコ人(音声では「カサブランカ」と呼んでいた)のように個人ではなく出身国を表す符丁で呼ばれていて、この現場での彼らの位置づけというか扱われ方が象徴されている。盗みを疑われることも含め、その鬱屈や不満が午後の休憩後の開店時間のはじめに爆発するのは、ジュリアが休憩を利用して中絶手術に行ったことを知ったペドロの怒りの表出という描きかた、でこのクライマックスの壮絶な盛り上がり方と哀しみが、ジュリアの抱えていたーペドロに応えられない秘密とともに最後を締めくくる緊張の作劇はなかなかすごくて目が離せず。原作の戯曲は未読だが、現代の社会状況をうまく反映して見ごたえのある作品に仕上がっている。モノクロ基調の狭い画面、印象的な音楽も併せて…。(6月28日 新宿武蔵野館170)
⑭ルノワール
監督:早川千絵 出演:鈴木唯 石田ひかり リリー・フランキー 河合優実 坂東龍汰 中島歩 2025 日本・フランス・シンガポール・フィリピン 122分
かつて大人の世界を目の当たりにして揺れ悩みしかしその表現においては秀逸さを示す少女といえば『お引越し』⑤(1993相米慎二)が思い出されるが、かの映画では両親の不仲は単に不仲の別離だったけれど、今回は父の「この夏を越えられない」闘病、母の職業上の不調(管理職なのだけれど部下からパワハラを訴えられるー夫の病を共に何とか乗り越え立ちと思いつつ夫の態度や自身の負担の重さに打ちのめされ越えられずに苦しむーというような中で感受性を大いに働かせながら表現のしようもなく、というか表現の真意を理解されることもなく表面上はあたかも流されるがごとく大人から見れば危なっかしい淵を歩きながら、何とか耐えてやり過ごす少女とある意味対照的に不安定な大人たちー夫をひょんなことから失った女性(河合優実)、少女と伝言ダイヤルでつながり自宅に連れ込むが…という青年(坂東龍汰)や心理学をベースとしたワークショップを運営して少女の母と危なっかいい関係を作ってしまう男(中島歩)らの暮らしぶりが物語というより少女の目から見た周辺に起こる散発的な出来事として描かれていくので、この世界に入れない人にとってはけっこうつらい(退屈な)時間かもしれないと思いながら、今の私にはなかなかに身につまされるところもある、生命力にあふれた少女と「死」の距離なのであった。病の父が娘と最後の?外出をした日、財布をなくしてタクシーで自宅に戻ると、部屋には妻の喪服がかかっているーその前に娘が喪服?らしいワンピースを着てみるシーンもあり、父の死や葬儀そのものは描かれない(しょっぱな少女が幻想する少女自身の葬儀が描かれるが)が、映画の間体中に死の気配が充満してしまうのは私の問題か?映画の秀逸さか?(6月27日 立川シネマワン 169)
⑬アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓
監督:マイケル・グルージャン 出演:マイケル・グルージャン ホビク・ケイチケリアン ネリ・ウバロア ナリーヌ・グリゴリアン ミハイル・トルヒン 2022アルメニア・アメリカ 121分 ★★★
都内4館くらいしか上映していないけっこうマイナーな映画みたいなのだが、あえて見に行ったのは、珍しい?アルメニア映画でしかもアララト山がモチーフになっているとのことだったから。とはいえ私の知っていたアララト山はトルコ側からみたもので、実はこの山昔からアルメニアの山だった…この映画の一つのテーマにもなっている20世紀初めのトルコのアルメニアに対する虐殺なども含む侵略の過程でアララト山はトルコ側の国境のうちに組み込まれてしまったまま、現代にいたるまでトルコとアルメニアには国交はない。そしてこの映画の時間は1940年代くらいだが、この時点でも現代でもアルメニア人にとってアララト山は自らの民族のアイデンティティにもつながる「心の山」ということだ。
トルコの侵略・虐殺をのがれ幼時にアメリカに渡りアメリカ人(アメリカッチ)として育ったチャーリー、彼は40年代、労働力確保のため当時アルメニアを支配したスターリンの政策により「帰還者」としてアルメニアに戻ってくるものの、ひょんなことからアメリカのスパイと誤解され捕らえられて刑務所送りとなる。ーすでにアルメニア語はほとんど忘れ、アルメニア側に英語がきちんとわかるものもいない、かつソビエト共産主義的官僚主義?の中で話がまったく通じず独房に放り込まれてしまう過程はなんというかつらいつらい見ものなのだが、監督自ら演じる主人公チャーリーのユーモアセンスというか楽天的志向は全編を貫いて映画内の人物はもちろん観客までをも共感させていく。彼の独房の高い窓外にはアパートがあってそこには大柄な男と美しい妻が住んでいる。実は洗濯物の腕章から、この男が刑務所の見張り塔に立つ看守で、かつ絵描きーアララト山の絵を沢山描いているーしかし、かつて高名な画家であったあったこの男はスターリン支配下で教会の絵を描いたことで摘発され、絵を描くことを禁じられて、妻の姉の夫かソ連支配下の高官であったため収容所送りは免れて看守をやっているのだということがだんだんわかってくる。
チャーリーは窓から見る二人の姿に自分を重ねて楽しみにしているのだが、やがて二人はケンカして妻は出て行ってしまう。この関係をなんとか修復したいと考えるチャーリーは元画家の看守にいろいろと苦労して連絡を取ろうとし、やがて看守の側もチャーリーの存在に気づいて二人の間に周辺の看守たちも巻き込んだ協力を得てひそかな交流が生まれる中段。
向かいの部屋の夫婦に子どもも生まれ、彼らを囲んで親族が集まって宴会をする。それを見ながらこちらの独房ではチャーリーが一緒になって自分の食事をしたり合わせて乾杯をするというような光景が切ない。そのなかで看守はひそかにエールを送り主賓への乾杯をささげてくれたり、そんな感じで描かれるが、やがてチャーリーら帰還者のシベリア送りが決まる…最後の方は彼を刑務所に送り込むきっかけとなった高官夫妻の刑務所訪問などもあり、チャーリーの運命如何という感じで話にはスピードが…。そしてスターリンの死後ようやく解放され国外に出ることを勧められつつ、そうはせず前に彼が見ていたアパートを訪ねてくるとそこはすでに空き家でテーブルクロスにひそかに描かれたアララト山。看守夫婦、あるいその妻の姉の高官夫婦は、スターリン体制の手先としてその体制が崩れたアルメニアにはやはり生きていく場所はなかったのだろうかと思わせられてしまうような、それでもチャーリーはアルメニアを愛するのだな、と帰還アルメニア人の心情の一環を感じさせられるような…。監督・主演のマイケル・グルージャンは帰還しなかった?アルメニア系アメリカ人で、祖父母はトルによる虐殺の犠牲になったのだとか…ユーモラスだが重いテーマの映画で心に残る。題名の「コウノトリ」は刑務所の屋根に巣を作っている。チャーリーの自由へのあこがれの象徴のようでもある。(6月25日 キノシネマ立川168)
⑫セルロイド・クローゼット デジタル・リマスター版
監督:ロブ・エブスタイン ジェフリー・フリードマン 出演:トム・ハンクス ウーピー・ゴールドパーク スーザン・サランドン シャーリー・マクレーン リリー・トムリン(ナレーション)1995アメリカ 102分 ★
この映画の日本初公開は1997年で、もちろんその時も意識はしていたが、結局見に行く余裕がなく見逃していた。一つにはこの当時まだ古いハリウッド映画をあまり見ていなくて、映画を見てもわからないところが多いかもと思ったこともあるような気がする。で、今回の初参戦。名前を上げたスターたちは出てくる映画に出演しインタビューを受けている人々(の一部)だが、インタビューはむしろ映画作家(脚本家)や批評家、製作者などの方が多くて、無声映画時代から95年当時までの120本のハリウッド映画を取り上げその中に描かれたり描かれなかったりするゲイやレズビアンの姿を映して関係者がコメントをするという形は、まさに映画史の中のクイアの描き方を俯瞰することができた、という意味で非常に興味深く見た。95年当時はまだエイズの恐怖か同性愛を覆っていたころで、映画の中での同性愛者の末路は決して明るくは描かれず、その中で『フィラデルフィア』(1993ジョナサン・デミ)とか『テルマ&ルイーズ』(1991リドリー・スコット)の「主張」が見られるようになった時期?『プリシラ』(1994ステファン・エリオット)は出てくるが、この映画にはまだ『ブロークバック・マウンテン』(2005アン・リー)は出てこない。その後の30年を考えると、今や映画の中のLGBTGの描き方って本当に変わってきていて、あの時代との隔世の感を感じる。とすれば『ハーヴェイ・ミルク』(1984)を作ったロブ・エブスタインのもう一つの仕事としてすごく意味のある作品なんだと思う。(6月24日 渋谷ユーロスペース167)
⑪シアトリカル 唐十郎と劇団唐組の記録
監督・脚本:大島渚 出演:唐十郎 鳥山昌克 久保井研 稲荷卓央 藤井由紀 赤松由美
2007日本102分
2024年亡くなった唐十郎が2007年66~7歳にかけて『行商人ネモ』の脚本を書き上げるところから稽古の過程のさまざまな様子や、参加している劇団員たちの意欲や屈託、この映画の描き手である大島クルーとの軋轢まで含んで大阪のに張った赤テントでの公演までを描いていくドキュメンタリー、という体裁だがエンドロールによれば7割がドキュメンタリー、2割はフィクション、1割は虚実不明だそうで、唐自身も最後に「自分を演じるのはむずかしい」とにやりという感じで、これが大島新の監督第一作として作られたということも、脚本を大島自身が書いているとクレジットされているところから見ても、ウーン、ま、ドキュメンタリーとは見ない方がいいのか…。大島自身が映画の中で唐に怒鳴られ、そののち和解して唐の芝居を演じる場面さえもあるが、これはむしろノンフィクションか?
ともかく、この唐という天才のもとで修業みたいに稽古に励み演劇の諸実務を背負う14人の40代以下の若者たちの姿は、自身が捨て去ってきたというか忘れてきたものを思い出させるけれど…。強い求心力を持った唐の死後、役者たちはどういう人生を歩めるのか見ていてちょっと心配になったが、映画のあとでネット検索したら今も唐組は唐の戯曲を演じて公演も行い、唐の戯曲は夫人が社長、子供たちが取締役に就任した有限会社唐組で管理していくのだそう。ただしこの映画では劇団の役者の代表みたいだった鳥山は今は劇団を抜けて活動しているとかで、ここにもドラマがあったのかな?となんか天才の死というものの意味を今更ながら考えさせられてしまう。映画中の赤テントの芝居は昔花園神社で見たころと雰囲気的には変わらず。私の見たころは多分小林薫とか麿赤児とかが出ていたころだと思うが、そのころはそういう人々を全然知らなかった。(6月24日 下高井戸シネマ166)
➉アンジーのBARで逢いましょう
監督:松本勤 出演:草笛光子 松田陽子 青木柚 田中偉登 六平直政 寺尾聡 2025日本88分
突然街に現れいわくつきの廃れたバーの建物を借りて、あたりに住むホームレスの手を借りて建物に手を入れて開業パーティにこぎつける老女アンジーのファンタジーというわけだが、まったくにファンタジーで、彼女は開業パーティのその日起こったトラブルで姿を消してしまう。ただ、この映画はアンジーというより彼女の周辺にかかわることになった人々、特に向かいで美容室を営む母とその高校生の息子の抱える屈託にアンジーが直接というよりはそのわけありげだが明るい接触で彼らの共感や助けを呼びその結果彼らの生き方をも変えていく?というような「彼ら」の側の物語で、それはアンジーが店の改造に巻き込む元大工や電気工事者、また不思議な暗黒舞踊の踊り手であるホームレスたちがアンジーが消えた後の生き方までも変えられていく姿や、女子プロレス志願の女性がアンジーを助けることによって自らの生き方に確信を持ち未来を切り開いていく姿などにも現れている。彼らの悩みは悪意があってや努力の結果でどうにでもなるものでも必ずしもないのだが、それでも気にせず生きて行こうよという老いて老いながらでもファンタジックに生を繋ぎ新しい世界に生きて行っているかのようなアンジーの姿に観客をも励まされるところ、なかなかの作劇でもあり、草笛光子の演技力というよりか草笛光子らしさかもしれない。映画そのものは思ったより地味?な作りのような気もするが、石田ひかりと木村祐一(近所のオカルト主婦と霊能者)、田中要次(刑事)、ディーン・フジオカ(謎の和装ライダー)らがチョイ役で色を添えている。高齢者映画?+ゲイムービー的要素もありひきつけ要素はたっぷり。(6月24日 下高井戸シネマ 165)
⑨ラブ・イン・ザ・ビッグシティ
監督:イ・オ二 出演:キム・ゴウン ノ・サンヒョン チャン・へジン 2024韓国118分
「いかれ女」(と映画の中で言われている)ジェヒは豊かな両親の恩恵を受けて家賃も知らずにまあまあの家に住んでいるが、親との実際の親密さはないようで「見放されている」というセリフもあるし、終わりの彼女の結婚式シーンにも親らしき人の姿は見えない。一方のフンスも父との関係は不明だが、母親はフンスに期待も希望も持って彼の「ゲイ」を病気と思って心配しているらしくちょっと過干渉の気あり。フンスはジェヒとのルームシェア以外の時は母の住む家に同居している。ということであまり見た人の感想にはないが、この親子関係ってけっこう彼らの「普通」ではない生き方に影を落としている気もする。ゲイを親にも他人にも打ち明けられないフンスというのは(映画の登場人物としては)フツウという感じだが、20歳のときには奔放で思いのままに生きているかのようなジェヒが、年を経てけっこうつらい立場に追い込まれていくー職場ではパワハラ・セクハラ的状況におかれ、できた恋人は支配的でDV的傾向さえ示すというのは、どうなんだろう、一つにはジェヒの最初と最後のウエディングドレス姿にも象徴されるような、結婚願望というか恋人がほしい願望(これはもちろんフンスにもあるのだろうが、彼はそれ以前にカミングアウトするかどうかの問題を抱え、それができないゆえに恋も成就しないところがある)の強さによるのではないかな、と、その意味ではジェヒは見かけほど「普通ではない」女性ではないような感じで、それがこの映画の甘さというか若い人を引き付ける要素にもなっているのかもしれないが、ジェンダー論的に言えばジェヒの中途半端さは(リアルなのかもしれないが)映画では見たくないよな、というか先に開いていく映画とは思えない。もう少し言えばジェヒの「普通でない」結婚生活というものが想像しにくいのである。『君の名前で僕を呼んで』や『ブエノスアイレス』が引き合いに出されているところからも、むしろゲイ・ムービーとして、フンスの成長譚とみるべきかも…。いずれビッグシティにはいろいろな男女(同性どうしも)の関係があるのだよなと思わせられるという意味ではなかなかに秀逸な題名だなとも思える。(6月22日 府中TOHOシネマズ 164)
⑧島から島へ(由島至島)
監督:廖克發 2024台湾(台湾語マレー語インドネシア語日本語…)290分 ★★
台湾では4時間50分の長尺にもかかわらず、上映のたびに完売、金馬奨でも2冠受賞、沖縄環太平洋国際映画祭でも上映されて話題になった作品。法政大学で授業の一環として行われた上映会での鑑賞。ウーン。内容的には第二次大戦中、日本統治下にあった台湾の、日本軍台湾人兵士の被害のみならず加害者としての体験を含めた戦争の記憶をインタヴュー(役者による「口述」=再現インタヴューも含め)一部当時の再現ドラマも交えながら、さまざまな視点からインタヴューや当時の写真などを連ねた映像で綴る。台湾からおもに軍属として志願したりあるいは徴用されたりしてマレーシアやシンガポールなどに送られた人々、この地での華人(共産党支持)と台湾からの兵士(当時は日本兵)の対立とか、日本軍の下っ端として現地の人々を弾圧殺戮した台湾人兵士が戦犯として処刑されたりとか、あるいはその子孫として現在もマレーシアに住む人々、元台湾人兵士の中にも日本軍の現地人虐殺などはなかったと言い切るものあり、もちろんその記憶に子孫ともども苦しむものあり。また広島(原爆被災地としてと、東南アジアに向けての軍用機地だった加害的側面と両方の性格を持つ)の日本人の発言とか、これでもかこれでもかという感じで多角的な視点で迫ってくるのがすごいとともに、エネルギー不足のみとしてはいささか応えてつらくなる場面もけっこう多かったが、これだけ言わなければ、言っても語りつくせないのだという作者や、かかわった人々の意識が画面からはみ出し語りかけていくような大力作だった。
終わりに主催者の法政大福田円教授、台湾映画の研究者三澤真美恵氏(日大)、それに映画にもかかわった藍適斉氏(国立政治大)がオンラインで座談会。藍さんの中国語のわかりやすさ、話の熱にひきつけられる。—映画に登場する彼の母上、またマレーシア在住の台湾人戦犯子孫というサイモンさんとの出会いについてなどで、映画との距離がぐっと近くなる。
意義ある上映会だったが、この長さだと劇場公開はどうなんだろう…日本軍や日本の帝国主義に関してはもちろん批判的立場だから、その点からも難しいのかな…とすれば残念。
なお、7月3日には廖監督を招いて法政大学でQAセッションが行われる予定だそう。(6月21日 法政大学上映会 163)
↓三澤真美恵さん/藍さん(画面)・福田円さんの会場/今回の上映画面
⑦舟に乗って逝く(乗船而去)
監督:陳小雨 出演:葛兆美 劉丹 呉洲凱 何必 2023中国99分
72歳の周瑾は徳清(浙江省湖州市)に一人暮らし、長男は若くして亡くなり、長女は米国人の夫と上海で英語学校を経営し、中学生の娘スーザンがいる。次男は父を継いで船大工?になりたかったのだが親に反対され進学して中国各地での観光ガイドになっている独身。長女には前夫との間に生まれた涛という息子がいて俳優を目指して家を出て自活している。というような家庭状況の中で母瑾が倒れ、余命宣告をされてしまうというのが話の始まり。
アメリカで最新の治療を受けさせたいという長女、母の意を汲んで故郷の家で介護をしようという次男。夏休み長女の夫と娘がアメリカを訪ねている間、長女と次男は結局故郷の家で介護体制を整えて自ら母を看取ることになる、その数か月(数週間かな?)が描かれる。母を訪ねて上海から弟(姉弟の叔父)が訪ねてきて、姉弟はこの叔父とともに母を下渚湖に連れ出し船で観光したりするが、母がかつて童養媳として買われてこの叔父の妻になるはずだったことが「養子と実子」「幼くて自分にはわからなかった」というような母・叔父のことばによって姉弟に知らされる。共産党政権後にそのような境遇を抜け出した瑾は自らの「帰る場所」を求めて大工の夫と結婚してこの地に住んだということで、彼女がこの地で死にたいという思いの強さが表され、また実父母の家を失い、自らの生きる場所として役者の道を求めている孫息子涛に対する祖母の思いの強さもなるほど納得。とまあ、人が生きる場所をどこに求め、また死にゆく場所をどこに求めるのかということが登場人物それぞれに若い者は若いものなりに老いたものは老いたものなりに求めていく姿が描かれて行くわけだ。話の展開としては意外性というようなものはなく、あくまでも老母のこの世からあの世への移行を世俗も心理の純粋さも含めて、意外に客観的に描いているーこの老母もお金はちゃんと持っているのだな…というのが最近見る「老人映画」の共通項でウーン。若者から見るとそれほどに高齢者は金銭的には豊かなのかな…。画面構成の端正な静けさ、水郷の景色などは目に染みる美しさ。人間関係的には実は次男の女友達?や見合い相手まで出てきてなんかゴチャゴチャしているのが果たして必要なのか??と思われるシーンもなくはない感じで少し混乱しないでもない。悪くはないんだけれど、やはり若い監督から見た老人観・死生観?という気もしなくもない。という大変に歯切れの悪い感想だが…あ、しかし隣に座った若い女性、さかんに鼻をすすり涙をぬぐう。そうなんだ…若い目で見るとね。(6月20日 アップリンク吉祥寺 162)
⑥テルマがゆく!93歳のやさしいリベンジ
監督:ジョシュ・マゴーリン 出演:ジューン・スキップ フレッド・ヘッキンジャー リチャード・ラウンドリー パーカー・ポージー クラーク・クレッグ マルコム・マクダウェル 2024アメリカ・スイス99分 ★
孫息子が事故を起こし刑務所に、保釈金が1万ドル必要という「本人」?と弁護士からの電話にお金を送金してしまい、典型的なオレオレ詐欺に引っ掛かってしまった93歳のテルマ。家族(娘夫婦)はテルマの老いを仕方ないものとして、彼女を1人で暮らさせるわけにはいかないー欧米だと娘と同居、ではなく老人ホームということになる??ーという方向に傾き、いつも祖母を慕い、また祖母にも可愛がられている孫息子(この孫息子運転やPCにはなかなか力を発揮するもの、失業中、人間関係もうまくいかず自己肯定感も低い青年で、その孫を唯一肯定評価するのが祖母テルマということになる。その意味で、テルマが犯人のことばを信じてしまうというのも納得いく?展開になっている)も親にはあらがえない。一方テルマは金を取り返すことを決意、弁護士から聞いた住所を探して、まずは旧友のベンの住む老人ホームを訪ね三輪スクータを乗り逃げのように借りようとするが、結局ベンも彼女について行く感じで犯人探しに、一方の老人ホーム側では入居者の老人と客の失踪ということでテルマの娘一家もホームに乗り込んで捜索…というわけで犯人探しとはいえ、そんなに胸のすくようなアクションになるわけではなく、テルマが頼ったり連絡を取ろうとする友人は皆死んだり、認知症気味だたったり(ベンを演じた映画では頼りになりそうなリチャード・ラウンドリーも亡くなって献辞が最後にでてくる)でなんか見ている方も本人も老いの悲哀を感じるようなシーンもあるのだが、それでも負けないテルマ、運にも恵まれついには犯人のアジト?に乗り込む。この犯人が『時計仕掛けのオレンジ』(1971スタンリー・キューブリック)の無頼青年マルコム・マクダウェル(チャンと面影があった)であるのもなんかなるほど。1万ドル奪われたテルマは、孫息子の電話指示に従って犯人のPCを操作、銀行口座から自身の口座へ振り込みを完了して金を取り返すが、それが9500ドルというのもなんかおかしくも納得。老人の自立のありようが何となく悲哀とともに示される感じがした。テルマ自身の強い意志もだけれど、それでも体は若い時のように動くわけではなく、むしろ彼女を取り囲む家族の状況や意識の方がこの映画の訴えていところかもしれない。実際に監督の祖母があった被害をもとに映画は作られているとかでその祖母自身(映画のテルマと全然タイプが違うが)がエンドロールに出演している。(6月17日 キノシネマ立川 161)
⑤国宝
監督:李相日 原作:吉田修一 出演:吉沢亮 横浜流星 渡辺謙 寺島しのぶ 高畑充希 森七菜 三浦貴大 見上愛 永瀬正敏 宮澤エマ 2025日本 175分 ★
たっぷりしっかり見せてくれる藤娘、鷺娘、二人道成寺、曽根崎心中などの歌舞伎舞台ーしかも演じるのが歌舞伎役者としてはいわば「素人」の吉沢、横浜というダブルYR?でそれが一瞬のもので長い訓練を経た歌舞伎役者のものではないながらも、それゆえに儚さとか一瞬の美のようなものを堪能させてくれるのを楽しむ。吉田修一が黒衣として歌舞伎の世界で3年間の取材をして書いたというのも驚きな原作をもとに作られているが、話の展開としては長い時間を描いているせいもあって、それほど目を奪うような話の流れでもない。もちろん丁寧に誠実に作られている感じはして見ごたえはまあ充分。特に前半は若い二人の舞踊や芝居での競演シーン以外には、むしろ二人の父であり師匠である渡辺謙と妻役の寺島しのぶ夫婦が主人公というか物語の芯を担っている感じも…。あと女形の世界を描いているからか、登場する女性たち(高畑・森・見上ら)の影は案外薄い感じ。もう一つどの人物も(国宝になった吉沢はちょっと??)何十年かの年の経過をちゃんと表すようなビジュアルになっているのもなかなかと思った。月曜昼の回というのにけっこう大きめのの会場満席に驚く。(6月16日 府中TOHOシネマズ 160)
④おばあちゃんと僕の約束
監督:パット・ブーンニティパット 出演:プッティポン・アッサラッタナクン(ビルキン)ウサー・セームカム サンヤ・クナコーン サリンラット・トーマス 2026タイ
3月大阪アジアン映画祭のラインナップだったと思うが、すでに劇場公開が決まっているということでスルーし、本日劇場公開初日の鑑賞ということに。「おばあちゃんの介護」というのがラクな仕事で、しかも介護をすることにより遺産(それも家?)が手に入るというムシのいい画策をして、祖母の家に押しかけ面倒を見る青年が、祖母との日常的な付き合いや他の家族との関係を見ながら、打算を捨て祖母と心を通じ合わせ…みたいな展開はなんか「祖母側」の立場としては、皆さんが言うように「涙」「涙」という感じにはならない。78歳のこのおばあちゃん、ガンで余命1年とか言われながら、独立心も旺盛だし、ちょっと皮肉だったり意地悪な機知さえもある感じで、映画の中での息子や娘の自分に対する扱いにイライラしたりムカッとしたりすることが多いだろうなあと思えるが、そこに主人公の孫息子が自身の打算(祖母を看取り遺産をもらう)も絡めつつ、祖母に共感していってしまうのがなかなか面白い。それにしても寡婦として長く生き、自身の食べ物店?をもっているとはいえ今も朝3時から仕込みをするというこのおばあちゃん、子供たちが狙いほしがるほどの財産を持っているのがタイ社会なのかしらん…親の負の遺産を子どもに引き継ぎたくないという中継的な立場で最近日々悩んでいたのだが、そんなことを悩んでも、その子供にさえ同情はされないのだろうなあと、ホワホワ感が漂う映画を見ながら考え込んでしまった。とはいえ、周辺からは鼻をすする音も複数聞こえてきて、やはり感動できないお年頃の自分がつらい…。(6月13日 新宿ピカデリー 159)
③ガールズ・ウイズ・ニードル
監督:マグヌス・フォン・フォーネ 出演:ビク・カルメン・ソンネ トリーヌ・ディフォルム ベーシア・セシーリ ヨアキム・フィエルスストロプ 2024デンマーク・ポーランド・スェーデン 123分モノクロ ★★
これは、なんといっても鮮烈な本当にくっきりはっきり陰影も深い白黒場面が大いにものを言っている映画だなあ。しかも音のおどろおどろしさ、第一次大戦中~後のコペンハーゲン、貧しいお針子カロリーネが追い込まれていく苦境は胸をつく。夫は戦争に行ったまま行方不明、工場主が夫の行方を捜しつつ彼女に言い寄り妊娠させるが、母親の冷たい無視の中でカロリーネは捨てられ職も失うことに。長い鋭い針を使い浴場で自ら堕胎中絶を図る彼女を助けたのがダウマという女性で、この女性の頼もしさ、生活や日常がきちんとしている雰囲気で、7歳?の少女の母としても威厳を持っている感じでいかにも頼りがいのありそうなのが、いわばこの物語の眼目だろう。自らの赤ん坊を養子に出すことをダウマに誘われ頼み、しかしその費用が全額は払えなかったことから彼女は預かった赤ん坊の乳母としてダウマに雇われることになる…。というわけで、赤ん坊の行方はマンホールに流れる水とか、盛んに燃やすストーブとかで間接的な示し方だがかえって生々しく怖く、法廷でのダウマの主張までものすごく正攻法で、今こそ福祉の行き届いた国の一つであるデンマーク社会の当時の女性の置かれた位置に抵抗する女としてのダウマ、その彼女の思いをきちんと受け止め自らの女性としての人生の選択をしていくのであろうカロリーネに、胸につまされるような思いとともに共感を持つ。戦争で顔半分を失い戻って、すでに愛人がいて妊娠した妻にも拒まれ、サーカスでいわば身売りのような見世物になりながら、しかし妻への愛というか同情を失わない夫の描き方に救いを感じさせるのは、この映画の若い(40歳くらい?)監督の男性目線かなと思われた。実際にあった殺人事件をもとにえがいているのだそう。(6月13日 新宿ピカデリー 158)
②盲目の目撃者(Bhramam)
監督:ラビ・チャンドラン 出演:プリトビラージ・スクマーラン マムター・モマンダス
2021インド(マラヤ―ラム映画) 146分
初っ端は森を疾走する黒猪と追う猟師。これが140分後の話に繋がっていく…前半は野猪はどこへやらで、盲目をよそおうピアニストのレイ、彼は映画監督の友人に頼まれ、結婚記念日のサプライズ演奏にその自宅を訪ねるが、友人が妻とその浮気相手に殺されているのを目撃してしまう。盲目をよそおい気づかぬふりでなんとかその場を回避するが…次の日、警察に告発のつもりで行くと、なんと警察署長が昨日の浮気相手だった、というわけで、盲目と気づかぬ相手(殺人者)の前で気づかせぬままなんとか殺人者を告発。断罪したいと願うレイと、相手が「見て」いるのかいないのか半信半疑のままになんとか目撃者の口を封じてしまいたい殺人者側のドタバタ攻防が後半の展開?になっていくわけだが、レイを拉致して腎臓を奪おうとする医者とか、レイに恩義を感じている人々とかが絡んで、レイ自身毒を盛られて本当に目が見えなくなったり、倒されて気を失ったりしながらもなんとか永らえてこの窮地を脱してーというのがすごい、なぜかというとこの事件で彼に絡んだ人々が殺人者たちも含め全員死んでいくという、ドタバタしていてあまり陰惨感はないのだが実に陰惨な構成になっている。最初の野猪シーンも実は…ということ。浮気相手(愛人という感じでもないみたい)と一緒に夫を殺し、その後もレイに毒を盛り、目撃者を殺しと悪を重ねる友人の妻が実質ヒロインで超美人の悪役振りすさまじく…。狂言回し的に何も知らずにレイに好意を持ち、盲目の偽装を怒って振り、そして2年後に再び彼と出会うという女性(アンナ?)の存在がまあ、救いといえば救い??インターミッション(実際には日本ではなくて表示のみ)付きのてんこ盛りインドドラマはついて行くだけで精いっぱいという感じもある。『盲目のメロディ〜インド式殺人狂騒曲〜』(2019 シュリラーム・ラガヴァン)のリメイクだそうだが、前作は未見。(6月12日 新宿K’sシネマインド大映画祭2025 157)
初っ端は森を疾走する黒猪と追う猟師。これが140分後の話に繋がっていく…前半は野猪はどこへやらで、盲目をよそおうピアニストのレイ、彼は映画監督の友人に頼まれ、結婚記念日のサプライズ演奏にその自宅を訪ねるが、友人が妻とその浮気相手に殺されているのを目撃してしまう。盲目をよそおい気づかぬふりでなんとかその場を回避するが…次の日、警察に告発のつもりで行くと、なんと警察署長が昨日の浮気相手だった、というわけで、盲目と気づかぬ相手(殺人者)の前で気づかせぬままなんとか殺人者を告発。断罪したいと願うレイと、相手が「見て」いるのかいないのか半信半疑のままになんとか目撃者の口を封じてしまいたい殺人者側のドタバタ攻防が後半の展開?になっていくわけだが、レイを拉致して腎臓を奪おうとする医者とか、レイに恩義を感じている人々とかが絡んで、レイ自身毒を盛られて本当に目が見えなくなったり、倒されて気を失ったりしながらもなんとか永らえてこの窮地を脱してーというのがすごい、なぜかというとこの事件で彼に絡んだ人々が殺人者たちも含め全員死んでいくという、ドタバタしていてあまり陰惨感はないのだが実に陰惨な構成になっている。最初の野猪シーンも実は…ということ。浮気相手(愛人という感じでもないみたい)と一緒に夫を殺し、その後もレイに毒を盛り、目撃者を殺しと悪を重ねる友人の妻が実質ヒロインで超美人の悪役振りすさまじく…。狂言回し的に何も知らずにレイに好意を持ち、盲目の偽装を怒って振り、そして2年後に再び彼と出会うという女性(アンナ?)の存在がまあ、救いといえば救い??インターミッション(実際には日本ではなくて表示のみ)付きのてんこ盛りインドドラマはついて行くだけで精いっぱいという感じもある。『盲目のメロディ〜インド式殺人狂騒曲〜』(2019
シュリラーム・ラガヴァン)のリメイクだそうだが、前作は未見。①秋が来るとき
監督:フランソワーズ・オゾン 出演:エレーヌ・バンサン ジョージアーヌ・バラスコ
リディビーヌ・サニエ ピエール・ロダン ガーラン・エルロス ソフィー・ギルマン
2024フランス103分 ★★
パリのアパートを娘に譲ったミッシェル(80歳)はブルゴーニュの田舎(堂々たる?1軒家で庭や菜園などもついていてなかなかの別荘風?)に一人住み、近所にいる「仕事仲間」だったマリ=クロードと仲良くしている。最初の場面はミシェルがマリ=クロードを乗せて「誰かの面会」にいくところ。次の場面では二人が森へキノコ採りに行く。午後、娘バレリーが孫息子ルカを週末に預けるためにやってくるが、ミシェルの出したキノコ料理を食べたバレリーが倒れ救急搬送されるという事件がおこり、「母に殺されるところだった」怒ったミシェルはルカを連れ帰り母との連絡も絶ってしまう。一方ミシェルとマリ=クロードが訪ねて行ったのはマリの服役中の息子ヴァンサン。彼はやがて釈放になり家に戻ってくる。ミシェルは彼に目をかけ自宅の菜園や庭の手入れなどの仕事を彼に与える。ヴァレリーの怒りとミシェルの意気消沈を心配したヴァンサンはパリのヴァレリーを訪ねるが、そこで「事件」が起きてヴァレリーはアパートのベランダから転落する―この事件の描き方はちょっと『藪の中』形式で、直接的には描かれずそれぞれの登場人物がどう見て、どう対応したのかということに主眼が置かれる謎めいた描き方なのだけれど、要は誰もが「疑惑」を持ちながらその疑惑をあらわにはせず、言ってみれば「善意の言い分」を信じることによって、少年ルカがおとなになって帰省し、ミシェルが彼にこの別荘のカギを与え、ルカやヴァンサンと森に出かけたミシェルが幸せな?死(天寿全うという感じ)を迎える大団円的に描かれる。
娘ヴァレリーの母に対する「敵意」は母の職業に関するもので、それによって育てられた娘ということからすればちょっと子供っぽい潔癖性という感じもし、いわばそれで彼女は身を亡ぼすわけだが、死後、母の前に亡霊として現れるという形で、セリフはないのだが母を贖罪するように描かれるのもちょっとオゾンっぽいか…。したしいはずの家族にゆえなき(というか、もちろん敵意を持つ側には何らかの理由があるのだろうが)というかそれほどの敵意を向けられる覚えのないような敵意を持たれてしまうつらさーときに相手が死んだら楽になる?いやいやもっとつらいのかもしれないと思えるような日常を過ごしている身としては、身につまされながら、だがああいうふうに皆がそろって(子どもや、登場する警部まで)行為の実態を突き詰めずにその善意だけを信じるようにすればミシェルは幸せに死ねるのか…とうらやましい気もするのだが、私の「若い」心はなんかキモチが悪い、という感じもして、すごく考えさせられる映画を見てしまった…。
ところで二つの家を持ち、車を乗り回し、娘に仕送りをし、ヴァンサンには仕事を与えカフェの開業資金を出し、孫の面倒も見るというミシェルの経済力にはリアリティがあるのだろうか、とそれも気になるところ。 (6月1日 新宿ピカデリー 156)





















.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
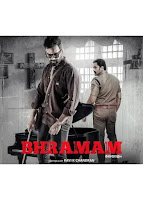

.jpg)


コメント
コメントを投稿